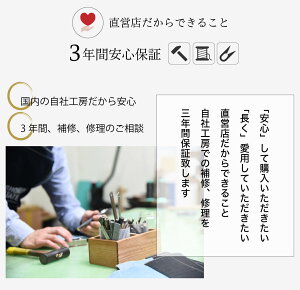今年、デンドロビウム・ギンギアナム系は見事に花をつけ、独特のよい香りがしていました。けれど、他の種類のものが、今年は花が付きません。楽しみにしていた花芽は、高芽に変わったしまいました。なぜだろうと思い、調べてみると、温度管理と肥料の与え方が原因だったようです。シンピジウムと同じようにしていたらダメでした。デンドロビウムの花を咲かせるための育て方、注意点を入れてご紹介します。同じ悩みをお持ちの方、参考にしてください。
デンドロビウムはこんなお花!
デンドロビウムは、洋蘭の中でも最も品種が多く、熱帯・亜熱帯のアジア・オセアニアに約1600種類が自生しています。姿形もバラエティーに飛んでいます。デンドロビウムは、木や岩などに根を張りつかせて育つ「着生蘭」です。品種改良の元となった原種名から分類されているそうです。

- 【ノビル系】原種ノビルを元に作られたもので、寒さに強く、枯れにくいので、洋蘭栽培の初心者にもおすすめの品種です。ノビル系の品種改良は日本がトップレベルで、新しい品種が次々と生まれています。日本原産の「セッコツ」との交配種も多くみられます。太い茎「バルブ」がまっすぐに伸びて、艶と厚みのある葉を茎の左右に出し、バルブの節々から短い花茎をのばしその先端に花を2~3輪ずつ咲かせます。1つの花が約1ケ月咲き続けます。
- 「デンファーレ系」オセアニアの原種ビギバムを元に改良されています。耐寒性が弱く、15℃以下になると育てるのが厳しいくなります。冬は日のよく当たる室内での管理になります。
- 「フォーモサム系」原種はファモサムで、バルブに細かな黒い毛が生えています。交配種「ファーミブル系」が一番多く流通しています。バルブの上の方に花を付けます。
- 「キンギアナム系」オーストラリアに自生している原種ギンギアナムを元に作られ、根元が太く上の方が細い硬いバルブに花をさかせます。香りの強い品種もあります。
〈広告〉
植え替えと株分けは4月頃が最適期
バルブの成長に伴って、どんどん根が伸び根詰まりの状況になります。根がすくすく成長できるように、一回り大きな鉢に植え替えか株分けをしましょう。植え替えと株分けは4月頃が最適期です。
材料は、水苔・バークチップ・ヤシガラチップなどに植えこみます。素焼きの鉢であれば水苔やヤシガラを、ビニール製の鉢は湿度管理が難しくなるので、バークチップと粒子の小さい洋蘭の用土を混合して使用しています。



【植え替え】
- 鉢と1時間水につけていた水苔を準備します。鉢の選び方はこちらをご覧ください。
- デンドロビウムを鉢から抜き出して、古い苔を取り除きます。
- 抜き出しにくいときは、鉢の外部からたたいてやると隙間ができて取り出しやすくないります。
- 根の先を傷つけないように、新しい水苔を根の周りに厚めにまき、新しい鉢に入れ込みます。
- 鉢の隙間には、さらに水苔をきつめに押し込んでいきます。そうすることで、鉢の中が安定します。
- 支柱を立てて、ビニタイを緩めにまきます。
- 植え替えが終了したら、水やりをします。水苔に水分はあるので、株全体に霧水を与えます。

〈広告〉
デンドロビウムは、肥料の与え方も花芽に影響!
洋蘭は一般的に、樹木に着生して繁殖することが多いため、それほど肥料を必要としません。かえって、与えすぎると逆効果になります。
春は、気温の上昇とともに新芽がぐんぐん伸びてきます。3月~7月までは、液肥は1週間~10日に1回、置き肥は、油粕と骨粉を混ぜたものを株に直接当たらないように1ヶ月毎に置きます。8月~9月半ばまでは肥料はストップしたままでも大丈夫です。
秋から冬にかけては肥料はそれほど必要としません。するとすれば、液肥を10日に1回くらいです。なのであげなくてもOKです。
植え替えをした場合は、1ヶ月してから液肥を開始します。8月以降、肥料を与え続けると花芽がつきにくくなります。
水やりは?
過湿過多にならないように注意が必要です。
もともとは、デンドロビウムは着生蘭ですから、多湿はどちらかというと苦手です。特にノビル系は乾燥気味の環境を好むといわれています。春になって成長を始めたら、徐々に水やりの回数を増やします。
バルブの根元から新芽が伸びてきたら、3日に1回のペースで、鉢の表面が乾き気味になったら水をやります。5月になって気温が上がってきたら、毎日1回、夕方以降の涼しい時間に、鉢底から水が流れ出てくるまでたっぷり与えます。夏は、乾燥が気になったら早朝にも水やりをして1日2回、たっぷりの水をあげます。
秋になったら、徐々に水やりの回数を減らします。冬は水やりの回数を控えめにし、乾燥気味に育てます。1週間~10日に1回の割合です。こちらも参考に。
戸外では、長雨に当たらないように注意します。バルブの成長がほぼ完成すると天葉という小さな葉が出てきます。その葉がでたら、水やりの回数を控え目にします。丁度このころから、前年育って出ていた葉は、黄変して葉が落ちてきます。
〈広告〉
置き場所は?
春~夏の時期
春、まだ花が咲いている時期はレースのカーテン越しの柔らかい陽射しの場所に置くと花もちがよくなります。花が終わると、気温が低い場合は、ガラス越しの日光がよく当たる場所に置き、5月半ば気温が上がってきたら戸外に出します。直射日光が強くなる場合は、葉焼けを起こすので30%の遮光をしてください。
もしくは、木漏れ日が当たり、半日陰になるようなところに移動してください。真夏は、棚の上に置くなどして、地面からある程度距離を置きます。

晩秋の低温処理が花芽を左右する
秋の低温処理が花芽の成長を促します。最低気温が10℃を超えてきたら、秋に気温が6℃前後になるまで屋外で管理します。晩秋に6℃前後の低温に1ケ月近く当たることによって花芽ができてきます。
屋内に取り込むものはぎりぎりまで待つようにします。これをすることで、花芽の分化が始まり、花が付きや安くなります。
11月半頃、花芽がバルブの節につき始めます。その際、乾燥しすぎないように霧水をします。

花後の処理は?
花が咲き始めたら、萎れた花は消毒したハサミで花茎の根元から切り取ります。そのままにすると根が出てくることがあり、バルブが痛む原因にもなります。

まとめ
デンドロビウムの花がつかなかった原因は、我家の場合は2つでした。
- 晩秋での3週間以上の体温管理ができていなかった。
- 肥料を8月以降もあげていた。
高めが増えたので株数は増えましたが、今回はこの部分の管理を注意し沢山の花を咲かせたいと思っています。同じ悩みをもっていた皆さん、来期は奇麗な花を咲かせて楽しみましょう。
〈広告〉